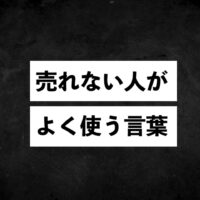昨日、ちょっと郊外の書店へと足を運んだ。
仕事の資料などを物色するためだ。
購入したのは、デザイン系2冊、マーケティング2冊。
久しぶりに1万円近くの購入。
本とは出会い。
これがリアル書店の強みだと思う。
今日はレジでの会計時の話。
僕の左側のレジに学生とおぼしき女性客が
会計をしていた。
僕は会計を済ませ、
商品をもらうまで待っていた。
待っている間、隣のレジの応対が聞こえてきた。
こんなやりとりだった。
女性客「(この書店の)ポイントカード使えますか?」
店員「実は、○月○日で終了してしまったんですよ」
あまりにも事務的なやりとりだった。
その女性客は、小さく
「あ、そうだったんですか、」
と話し、会計を済ませていた。
僕はちょっと違和感を感じていた。
(このお店の常連でもないし、ポイントカードも持っていない)
詳しい仕組み自体は分からないのだけど、
違和感を感じたのは店員の当たり前というような態度だった。
相手が学生の客だからという感じでもない。
ポイントカードは終了しました。
使えません。
ただそれだけを伝えたに過ぎない。
あくまで事務的に。
僕は思う。
こういう時こそ客の立場になって考えるべきだ。
大体ポイントカードは客の囲い込みの一環で
お店が始めるのがほとんど。
客のメリットも当然ある。
だけれど、その制度自体止めるのも
店舗の都合だ。
このお店のシステムは分からないが、
名前、住所なども収集するケースもある。
僕が違和感を感じるのは、ポイントカードなどを
廃止する時ほど、お店側がしれっと止めることである。
例えば、(しているのかもしれない)
メールでお知らせするとか、
住所をもらっているならハガキで伝えるとか。
ましてや、都合で止めるのであれば、
客側に対して少しは、
「申し訳ありません、、」の姿勢はあってもいいと思う。
終わりました。
以上。
ではない。
姿勢というのが大事だと思う。
他の人からしたら、
どうでもいいことかもしれないが、
僕はいつも「お客側」から現象を見ている。
驚くべきは売り手がまったくその事について
なんにも感じていないことだ。
これには本当に驚く。
書店の閉店が止まらないけれど、
アマゾンがどうとかいう問題以前に
もっとやれることはあるんだと思う。
それと僕はポイントカードという制度は嫌いだ。
これも機会があったら熱く語りたいが、
今日はこのくらいにしておこう笑
まさに今回の件は、
売り手の都合は、買い手の不都合。
の良い例だ。
仕事というのはルーチンになってしまうと
見えなくなってしまうことが多い。
店舗のマニュアルもお店側のオペレーションだけのことも多い。
だからこそクレームも起こる。
客側に立っていないからだ。
客側に立っていないから気づかない。
気づけない。
気づくか、
気づかないか。
盲点というのは当然放置される。
放置も何も見えない。
盲点というのは、タチが悪い。
見えないものは改善できないからだ。
今回感じた点は、
1)店側の都合が多すぎる
2)いつも客側に立って物事を見ること、姿勢を見せること
の2点。
いつだって売上をつくるのは、
売り手からの施策でもなんでもない。
お客様の行動だけだ。
細かいことかもしれなけれど、
こういう積み重ねでお客さんは離れていく。
まだクレームを出してくれればいいほうだ。
ほとんどがサイレントで去っていく。
これが一番こわい。
売るために、
売り続けるために。
何を「快」とお客様は感じるのか。
その一点にしか答えはない。
しかし、前述のような応対をしながら、
口では「お客様視点で!」などと言っている所は多い。
あなたはどうだろうか?
urapyon